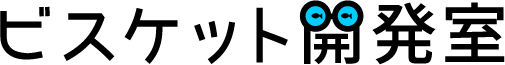長らく停滞していたこの「ビスケット開発室」ですが、書きたいことも溜まってきたので、ぼちぼち書き進めていこうと思います。
まずは、新しくリリースしたビスケットの概略について。
Appleの開発者向けサイトを見ると、以前のバージョンのiOSアプリが最後に更新されたのは2020年4月10日だったようです。ちょうど、コロナ禍が始まり、日本中の小学校が新学期から休校になった頃ですね。このアプリはAdobeのActionScriptという言語(Flashに使われている)で書かれていて、すでにFlashの廃止も発表されていたので、その半年くらい前から新しい開発環境でビスケットを作り直す準備を進めていました。この時点ではまず、旧アプリと見た目は同じだけど中身が違うものを提供する、という構想でした。
世界中がコロナ禍で大きく方向転換したように、ビスケットも単純な置き換えではなく、新時代にフィットするものを提供しなくては、と考えました。GIGAスクール構想の前倒し(高学年から順にタブレットを配備する予定だったものを、全学年に一斉配備することに)、当時の文科省の方が「ハードウェアだけじゃなく、ソフトウェアにも予算をつける」とおっしゃっていたこと、「義務教育でのプログラミング教育の必修化」という、3つの要因が重なり、旧アプリと同じく個人向けではなく、学校向け、つまり教室で使用することを前提としたビスケットを提供することにしました。中身はオンラインで授業ができる仕組みです。児童のビスケット上での操作は先生の画面で一斉に見ることができます。1操作ごとに小さなデータを送るだけなので、弱いネットワークでも全員分をサクッと集められるのが最大の特徴です。
それから6年間、いろいろとありまして、これまで全然目を向けてこなかった個人向けにも、ちゃんと取り組もうという考えで提供することになったのが、今回の新ビスケットになります。コロナがなければ6年前に出ていたかもしれないものです。そして、このブログの更新頻度が下がったのも、この時期と一致していますね。
コロナ禍でもう一つ、2020年3月ごろに緊急で開始したのが「はらっぱ」という仕掛けでした。この「はらっぱ」という名前は、さらに10年くらい前に、子供向けのデジタル創作ツールを作っているアーティストたちと組んだ集まり「デジタルはらっぱ」にルーツがあります。広場で駆け回るように、デジタルの中で作って遊ぶのも、これからの子供たちにとっては同じ「遊び」だよね、というコンセプトです。2020年頃には、その「デジタルはらっぱ」の活動も休眠状態だったのですが、コロナ禍で外出できなくなった子供たちに、私たちができることとして、この「デジタルはらっぱ」のコンセプトはぴったりだと思いました。そこで、旧ビスケットの仕組みのなかでできることとして、子供たちに解放しました。
それまでのビスケットには、自分の作品を取っておく仕組みはなく、ネットに作った作品をアップロードするだけでしたが、「はらっぱ」では、作った作品を簡単に修正して、さらにアップロードできるようにしました。ビスケットにはアカウントの考えがなかったので、誰の作品でも修正してアップできます。
「はらっぱ」で起きたことについては、また別に整理したいと思います。数年前からサーバーが溢れて作品を消し始めましたが、実はひとつも消していません。圧縮して、別のサーバーにきちんと保管してあります。いつでも見返すことができます。この「はらっぱ」では、いろんなことが起きました。最初は作品に対して感想を添えたコメントが寄せられていましたが、荒らしやなりすまし、NGな作品、いじめなど、想定されるさまざまなことが起きたようです。ただし、もともとそういったやりとりを目的としたシステムではないので、他のコミュニケーションツールのように爆発的に使われたわけではありませんでしたし、その合間にはすごい作品も投稿されていましたし、子供らしい楽しそうなやりとりもたくさんありました。
この「はらっぱ」を停止するのは、楽しんでくれた子供たちには申し訳ない部分もありましたが、もともとアカウント機能のないアプリでの参加者同士のやりとりにはリスクがあることは十分認識したうえでの、コロナ禍の緊急対応という側面もありました。ここまで引き延ばして運営してきたことは、ある意味すごいことだったなとも思います。
いまのところ、新アプリ内での参加者同士の作品のやりとりは予定していません。URLの発行機能だけは用意したので、もし何かの掲示板への書き込みが許されているなら、発行したURLを貼り付けてやりとりしてください。オンラインで知らない子供同士が出会うことは想定していませんが、子供たちがタブレットを持ち寄って一緒に遊ぶことは想定しています。
今回のビスケットは、作品を作ることにフォーカスしました。ビスケット本体の拡張も、絵やメガネが大量になったときに整理できるなど、複雑なプログラムを作る際に便利になるような機能が中心です。
もう一つの特徴は「アプリ内アプリ」という考え方です。ビスケットのアプリを立ち上げると、いくつかのカードが見えて、そこから別のアプリが開きます。作品を作るだけでなく、作品を作る目的や設定、できあがった作品の見せ方までをセットにしたものを「アプリ内アプリ」と呼んでいます。たとえば、「ビスケットランド」は、何人かで作った作品を一斉に集めて見せる仕組みですが、テーマが「うみ」の場合、背景色を決めて、作品をそれぞれ作り、投稿することで、みんなが作った「うみ」を見ることができます。

「うごくえほん」は、一人でも絵本が作れますが、何人かで分担して作ることもでき、できたページを並び替えて1冊の絵本にします。これらは、子供たちがタブレットを持ち寄って、みんなでワイワイ言いながらビスケットで遊ぶことを想定しています。「カレンダー」は一人で作りますが、毎日1作品ずつ作っていくこと、できたカレンダーはそれぞれの画面が動いて見えることが特徴です。自分が決めたテーマで、綺麗な模様を作り続けるのも良いですし――。
「アプリ内アプリ」の正式名称はまだ決まっていません(この呼び名もいまいちですが)、今後も拡張の計画をしています。お楽しみに。